goma-dango log
🥞☕
カテゴリ「ss」に属する投稿[6件]
2646文字, 2025.11.18 22:35 ss
Klavier
#akty 2025.11.24-26webオンリー初出
その夜二人が訪れたcrase cafeは、見慣れたものと異なる様相をしていた。
あたたかみのある照明は鈍く落とされ、どこか豪奢で艶っぽい雰囲気を醸し出している。暗い店内でも一際目立つのは、奥に鎮座するモノクロームの巨体だ。その鍵盤は青い歌声と共に奏でられ、赤い声色が旋律に寄り添う。カウンターでは心地良さげな桃色のハミングが重ねられている。二人はひとつ頷きあい、そのまま店内に満ちる音楽に耳を澄ませた。
――鍵盤が打ち鳴らした最後の音。それを聞き届けて、冬弥は手を鳴らしながら店内へ歩み入った。彰人も冬弥に続いてカウンター席に腰を下ろす。
「冬弥くん彰人くんいらっしゃーい!」
「いらっしゃーい!」
カウンターに座っていたルカが隣に座った冬弥に向かって腕を広げ、いつの間にか来ていたカイトが彰人の隣に座る。メイコはカウンターに戻って二人に微笑みかけた。
「お邪魔します。気分転換に彰人と待ち合わせたんですが、このような素晴らしい歌が聴けるとは思いませんでした」
「ああ、すげー聴き入っちまった。カイトさん、歌うとほんと普段と印象変わるよな……つか、どうしたんすかこの店」
彰人が内装に目をやる。その印象は、バー営業をしていた時のWEEKEND GARAGEに少し似ていた。
「杏ちゃんたちから聞いたよ! 冬弥くん、ジャズバーでピアノ頼まれたんでしょ?」
「だからここもジャズバーみたいな雰囲気にできないかなって、いじらせてもらったんだ!」
「ほら、飲み物もカクテルなんだよ!」
自由人二人がカラフルなグラスを慣らしながら楽しそうに語る。店にミクやリン、レンがいないのも酒があるのが関係しているのだろうか。
「カクテルって……つかここ酒あったのか」
「もちろんよ。『とっておき』をご馳走しようとしたこともあったでしょう?」
ノンアルコールも作れるから安心して。いたずらっぽくメイコが笑う。ウイスキーグラスに入れた烏龍茶を出してきたときのことを示され、彰人は小さく笑った。隣をうかがうと、冬弥は顎に手を当てて微かに首を傾げている。
「どうした?」
「……ジャズバーの話は、もしかしたら少し誤解があるかもしれません」
「え?」
なになに? と身を寄せるルカに、冬弥は口を開く。
「依頼を受けたのは事実です。お世話になっているライブハウスの常連客が経営しているジャズバーで、そこの看板歌姫の曲の伴奏を弾かないか、と」
Vivid BAD SQUADはストリートユニットとして名を馳せているが、そのファンの中にも音楽全般に造詣が深く、冬弥の出自を知っている人も当然いる。ストリートの世界でも、その演奏を求られることになるのは想像できたことだった。
けれど、ここにいるのは、ピアニストの青柳冬弥ではないので。
「一曲だけなら、伴奏を引き受けたい。ただし、歌姫の伴奏ではなく、歌も任せていただけるなら。そう答えました」
ボーカルユニットのBAD DOGSとして。
三人の感嘆の声が重なる。冬弥自身、全く別の要求をしていることはわかっていた。それでも歌を評価されている自負はあったし、演奏を見せないとも言っていない。果たして、Vivid BAD SQUADのファンでもあった依頼主は、二人の出演を受け入れてくれたのだった。
「彰人くんもそれでいいんだ?」
カイトが彰人を伺う。そりゃ、まぁ。彰人は相槌で応える。
最初に話を聞いた時は、まともに知らない歌姫とやらに冬弥の音楽の源をくれてやれるものか、と思った。けれど、冬弥自身が「BAD DOGSとしてなら」と言ったというのだ。彼の大切に抱えたはじまりの音楽を彰人となら歌いたいと。
それは、とても。
「人前で演奏するっつーのはちょっと驚きましたけど。今回はあっちが決めた曲らしいが、冬弥と歌えんならそれでいい」
冬弥がいいなら。彰人は店の奥を見やる。先ほどの曲で、カイトが奏でていた鍵盤。
「やっぱり、気になったかしら」
彰人の視線に気付いてか、メイコがカウンターに肘を付く。
「実はね、しばらく前からあったのよ。……きっと、冬弥くんのピアノ――クラシックへの気持ちが前向きになったからでしょうね」
セカイはあなたたちの想いで変わるものだから。メイコの言葉に冬弥が穏やかに微笑む。
「自分でも、前向きになったと思います。……今回のお話を経て、やってみたいこともできました」
今なら、クラシックもそれ以外も、すべての音楽を愛おしいと感じられる。これまでの経験も何もかもが、己の道と定めた歌の、世界への足掛かりになるだろう。だから。
「いつか、俺たちのイベントでピアノを演奏するなら。俺が作った曲を、俺自身が、相棒と、仲間と歌う曲でありたい」
力強い宣言に、彰人は相棒を見つめていた目を見張った。冬弥が彰人を見る。挑戦的な笑顔。彰人が惹かれてやまない、上へ行くという決意を湛えた瞳。
「彰人」
付き合ってくれるか?
答えなんてわかっている、そう物語る瞳を見て、身体に震えが走る。以前よりずっと、感情を表に出すようになった。未来に彰人を望むと口にするようになった。変化そのものにも、その変化に少なからず関わってることにも、言いようのない興奮を覚えている。
無論、答えは決まっている。
「当然だろ」
冬弥の原点と、共に見る夢を重ねて、託してくれる。
誇らしくこそあれ、厭うはずがなかった。
#akty 2025.11.24-26webオンリー初出
その夜二人が訪れたcrase cafeは、見慣れたものと異なる様相をしていた。
あたたかみのある照明は鈍く落とされ、どこか豪奢で艶っぽい雰囲気を醸し出している。暗い店内でも一際目立つのは、奥に鎮座するモノクロームの巨体だ。その鍵盤は青い歌声と共に奏でられ、赤い声色が旋律に寄り添う。カウンターでは心地良さげな桃色のハミングが重ねられている。二人はひとつ頷きあい、そのまま店内に満ちる音楽に耳を澄ませた。
――鍵盤が打ち鳴らした最後の音。それを聞き届けて、冬弥は手を鳴らしながら店内へ歩み入った。彰人も冬弥に続いてカウンター席に腰を下ろす。
「冬弥くん彰人くんいらっしゃーい!」
「いらっしゃーい!」
カウンターに座っていたルカが隣に座った冬弥に向かって腕を広げ、いつの間にか来ていたカイトが彰人の隣に座る。メイコはカウンターに戻って二人に微笑みかけた。
「お邪魔します。気分転換に彰人と待ち合わせたんですが、このような素晴らしい歌が聴けるとは思いませんでした」
「ああ、すげー聴き入っちまった。カイトさん、歌うとほんと普段と印象変わるよな……つか、どうしたんすかこの店」
彰人が内装に目をやる。その印象は、バー営業をしていた時のWEEKEND GARAGEに少し似ていた。
「杏ちゃんたちから聞いたよ! 冬弥くん、ジャズバーでピアノ頼まれたんでしょ?」
「だからここもジャズバーみたいな雰囲気にできないかなって、いじらせてもらったんだ!」
「ほら、飲み物もカクテルなんだよ!」
自由人二人がカラフルなグラスを慣らしながら楽しそうに語る。店にミクやリン、レンがいないのも酒があるのが関係しているのだろうか。
「カクテルって……つかここ酒あったのか」
「もちろんよ。『とっておき』をご馳走しようとしたこともあったでしょう?」
ノンアルコールも作れるから安心して。いたずらっぽくメイコが笑う。ウイスキーグラスに入れた烏龍茶を出してきたときのことを示され、彰人は小さく笑った。隣をうかがうと、冬弥は顎に手を当てて微かに首を傾げている。
「どうした?」
「……ジャズバーの話は、もしかしたら少し誤解があるかもしれません」
「え?」
なになに? と身を寄せるルカに、冬弥は口を開く。
「依頼を受けたのは事実です。お世話になっているライブハウスの常連客が経営しているジャズバーで、そこの看板歌姫の曲の伴奏を弾かないか、と」
Vivid BAD SQUADはストリートユニットとして名を馳せているが、そのファンの中にも音楽全般に造詣が深く、冬弥の出自を知っている人も当然いる。ストリートの世界でも、その演奏を求られることになるのは想像できたことだった。
けれど、ここにいるのは、ピアニストの青柳冬弥ではないので。
「一曲だけなら、伴奏を引き受けたい。ただし、歌姫の伴奏ではなく、歌も任せていただけるなら。そう答えました」
ボーカルユニットのBAD DOGSとして。
三人の感嘆の声が重なる。冬弥自身、全く別の要求をしていることはわかっていた。それでも歌を評価されている自負はあったし、演奏を見せないとも言っていない。果たして、Vivid BAD SQUADのファンでもあった依頼主は、二人の出演を受け入れてくれたのだった。
「彰人くんもそれでいいんだ?」
カイトが彰人を伺う。そりゃ、まぁ。彰人は相槌で応える。
最初に話を聞いた時は、まともに知らない歌姫とやらに冬弥の音楽の源をくれてやれるものか、と思った。けれど、冬弥自身が「BAD DOGSとしてなら」と言ったというのだ。彼の大切に抱えたはじまりの音楽を彰人となら歌いたいと。
それは、とても。
「人前で演奏するっつーのはちょっと驚きましたけど。今回はあっちが決めた曲らしいが、冬弥と歌えんならそれでいい」
冬弥がいいなら。彰人は店の奥を見やる。先ほどの曲で、カイトが奏でていた鍵盤。
「やっぱり、気になったかしら」
彰人の視線に気付いてか、メイコがカウンターに肘を付く。
「実はね、しばらく前からあったのよ。……きっと、冬弥くんのピアノ――クラシックへの気持ちが前向きになったからでしょうね」
セカイはあなたたちの想いで変わるものだから。メイコの言葉に冬弥が穏やかに微笑む。
「自分でも、前向きになったと思います。……今回のお話を経て、やってみたいこともできました」
今なら、クラシックもそれ以外も、すべての音楽を愛おしいと感じられる。これまでの経験も何もかもが、己の道と定めた歌の、世界への足掛かりになるだろう。だから。
「いつか、俺たちのイベントでピアノを演奏するなら。俺が作った曲を、俺自身が、相棒と、仲間と歌う曲でありたい」
力強い宣言に、彰人は相棒を見つめていた目を見張った。冬弥が彰人を見る。挑戦的な笑顔。彰人が惹かれてやまない、上へ行くという決意を湛えた瞳。
「彰人」
付き合ってくれるか?
答えなんてわかっている、そう物語る瞳を見て、身体に震えが走る。以前よりずっと、感情を表に出すようになった。未来に彰人を望むと口にするようになった。変化そのものにも、その変化に少なからず関わってることにも、言いようのない興奮を覚えている。
無論、答えは決まっている。
「当然だろ」
冬弥の原点と、共に見る夢を重ねて、託してくれる。
誇らしくこそあれ、厭うはずがなかった。
2302文字, 2025.11.18 22:34 ss
その赤の理由でありたい
#akty
そもそもの始まりは、オレが気付いてしまったことだった。セカイのカフェで合流したとき、こはねの印象がいつもと違う気がしたから。
丸テーブルの向かい側、背を屈めて軽く顔を覗き込もうとする。
「……し、東雲くん?」
「ちょっと彰人、何こはねにちょっかいかけようとしてんの!?」
ばしん。頭に鈍い衝撃が走って、オレの顔は強制的に下を向かされる。誰がやったかなんて、考えるまでもない。
「お前……」
起き上がったオレは当然杏を睨むが、当人はどこ吹く風だ。まぁ、でも、違和感の理由はわかった。叩かれる一瞬前、目元が淡くきらめいたのが見えたから。
「悪いこはね、なんかいつもと違えなって思ったから。メイクしてんだな」
疑問が解決したからと手元のセトリに戻そうとした意識は、テンションの高い声に引き戻される。
「そう! かわいいでしょ!? さっきあんたたちが来る前に二人でメイクしあってたんだよねー!」
横から抱きついた杏がこはねに頬を寄せる。並んだのを見れば、確かに似たようなパール感の色違いをまぶたに乗せているのがわかる。
いわく、どこかのアイシャドウの限定色がこはねに似合いそうで、しかもパッケージがハムスターイメージときて、どうしてもこはねに使いたくなったらしい。
「昼休みに瑞希が見せてくれたんだけどさ、私に似合いそうなのもあるって言うから。だったらお互いにやりたいなって。ねーこはね?」
「うん、人気だって聞いたから手に入らないかと思ったけど、近くで買えてよかった。フォトコンテストのときの青柳くんと遥ちゃんを見てたから、私もちょっとやってみたかったんだ」
こはねの言葉にオレの隣の冬弥が小さく微笑む。
「そう言ってもらえるのは嬉しいな。……しかしそうか、暁山が楽しそうに白石に会いに行くと言っていたのはそれだったのか」
なるほど、と冬弥が頷く。あいつ確かに今日は昼からいたな。学校来る目的が勉強じゃねえのかよ。自分も勉強は好きじゃないことを棚に上げて考えていると、杏が妙なことを言いだした。
「でさ、さっき話してたんだけど。そのうちイベント出るとき四人でメイクしてみない?」
「……は?」
何言ってんだこいつは。反射的に声に出た。
「限定品とかって色々コンセプトあるでしょ? イベントとか曲のイメージに合ったときとかさ、意識してみるのもいいんじゃないかなって!」
楽しそうな提案の途中、オレははっと気付いて隣を伺う。何せ、そこにいるのは好奇心の塊なのだ。果たして。
「それはとても興味深いな……!」
オレは頭を抱えそうになった。
わかってた、こういうヤツだ。オレの相棒は、初めての経験に興味津々だった。こうなったらもう、アレだ。ほら、俯いたオレを冬弥がチラチラ見ている。わかってるよ、オレはお前に弱いんだ。だから、
「彰人……駄目、だろうか……」
***
つーわけで、やるとなったら中途半端は性に合わねえ。オレらも有名になってきたし、ナメられないためにも見た目も強くしておくのも悪い手じゃないだろう。もちろん、一番は歌でわからせてやることだが。
幸いウチには姉貴の私物っつー参考資料もあるし、メイクは専門外でもコーディネートにはそれなりに自信もある。目的に合わせて演出するって意味じゃ考え方は近いはずだ。
オレが選んだ服、あの白い肌、綺麗な顔の作りを活かすなら。
「よし、やるぞ」
ベッドに座らせた冬弥の前、オレはアイシャドウブラシを構えていた。
「よろしく頼む……?」
冬弥はどこか戸惑っている。最初渋りそうだったオレがここまでやる気になったらそうなっても当たり前だろうが。オレは横に置いたパレットを確認して、冬弥に向き直る。
下地はすでに塗らせた。っつっても、こいつの肌は白くてきめ細やかで、必要ねーんじゃねーかってくらい綺麗だ。
「んじゃ、触るぞ」
一言落として、冬弥の頬に手を添える。下から覗き込んだ相棒の表情が変わった。目を伏せる一瞬、多分オレしか気付かない、ほんのわずかな色。
――そういうことかよ。ほんのひとしずく未満のさみしそうな瞳に、オレは何度呼んだか知れない名前を口にした。
「とーや」
ブラシを当てようとした手を下ろして、ひとつ息を吐き出す。
「別に、お前のメイクが駄目ってわけじゃねーからな」
「……え」
開かれたアイスグレーがオレを見る。そんなん、当たり前だろーが。
そもそも、こいつは自分でしたメイクでフォトコンテストに入賞したんだ。冬弥の表情はもちろん、こはねの写真も良かったにしても、メイクの協力者はあの桐谷だ。オレにあのトレーニングメニューを組んできた桐谷の教え方で、この勉強熱心な真面目バカが取り組んだらどうなるか。写真を見てなくたって、質がいいものになるのはわかりきっている。
「まぁ、専門外のオレがどうこう言えたもんじゃねえけど。でも桐谷にも暁山にも褒められたんだろ。そのお前のメイクが良くなかったわけあるかよ」
そこまで言い切ると、冬弥は顎に手を添えて首を傾げた。
「……では、なぜ彰人は俺にメイクをしてくれようとしているんだ?」
「そんなもん決まってんだろ」
本当にこいつはオレがメイクにもの申すためにやろうとしてたと思ってたんだろうか。理由なんて、その他にいくらでもある。
「メイクってのも要するに外見をどう見せるかって話だからな、ある意味コーディネートの延長線上みたいなもんだ。で、お前の服選んでんのはオレだろ。それなら無関係でいたくねえ」
だから、オレも冬弥のメイクをしてみたかった。まっすぐに冬弥の目を見て言う。
「……っつっても、さっきも言ったが、少しは調べはしたがオレはメイクは専門外だからな。実際自分であんだけやったお前よりはできねえと思う。なんかちげーなとか嫌だなって思ったら容赦なく言えよ。お前に我慢させてまでやりたいわけじゃねえから」
頼りにしてるぞ、相棒。オレの言葉を受け止めた冬弥は、目に見えて嬉しそうに表情を輝かせる。
「そう言ってくれるなら、彰人に任せよう。出来上がりを楽しみにしている」
「ん。じゃあ目ぇ瞑れよ」
ああ。小さな相槌のあと、銀色が見えなくなって、長いまつげの影が落ちる。そっと、白い頬に手を添える。
コーディネートの延長線上、だから無関係でいたくない。冬弥に言ったことは本当だ。だけど、それだけでもない。
冬弥は綺麗だ。本人に自覚はなさそうだが学校でもモテてるし、イベントに来てくれるファンの中にだって容姿を見てるヤツらはいる。ましてあんなコンテストに入賞して、メイクでもっと綺麗になることも、それが評価されることも証明されてしまっている。
その冬弥がメイクをするっていうなら。もっと綺麗になるなら、それで注目を浴びるなら。その冬弥はオレが手を加えた冬弥であって欲しい。冬弥をより魅力的にしたのはオレだって、こいつを見るヤツら全員に思い知らせてやりたい。歌やコーディネート以外のことでも、ぜんぶ。
冬弥は目を閉じて、オレに頬を触らせている。全幅の信頼だ。お前の相棒がこんなどろどろしたもんを抱えてて、何されてもおかしくない状況だってのも知らずに。
艶やかな唇に親指を近付けて、結局触れずに頬に添えた。
「……そういえば、お互いにメイクをしたと、白石は言っていたな」
「ん? ああ、そうだったか」
発端となった日のことだろう。確かにそんなことを言っていた気がする。
「なら、彰人のメイクは俺がしたい」
「……は」
今度こそ冬弥の頬に色を乗せようとしていた手が止まる。それを気配で感じたのか、冬弥が目を開ける。至近距離、きらきら揺れるアイスグレー。
「歌うときの彰人はとてもかっこいいから。彰人も認めてくれた俺のメイクで、彰人をもっと魅力的にすることができるなら、気分がいいだろうと思ったんだ」
そんなことを、楽しくて仕方ないって微笑みで口にするから。
「……おー。んじゃ頼むわ」
「任せてくれ。……すまない、邪魔をしたな。続きをしてくれ」
ふたたび目を閉じた冬弥は、さっきより機嫌が良い。ブラシを持った手に冬弥の息がかかって、距離の近さに今更気付いて唾を飲み込む。
冬弥にメイクされるってことは、目閉じたオレの至近距離にこいつの顔があるってことだよな。そのときの自分がどうなっているのかを少し不安に思いつつ、オレはメイクすることへ意識を向け直した。
#akty
そもそもの始まりは、オレが気付いてしまったことだった。セカイのカフェで合流したとき、こはねの印象がいつもと違う気がしたから。
丸テーブルの向かい側、背を屈めて軽く顔を覗き込もうとする。
「……し、東雲くん?」
「ちょっと彰人、何こはねにちょっかいかけようとしてんの!?」
ばしん。頭に鈍い衝撃が走って、オレの顔は強制的に下を向かされる。誰がやったかなんて、考えるまでもない。
「お前……」
起き上がったオレは当然杏を睨むが、当人はどこ吹く風だ。まぁ、でも、違和感の理由はわかった。叩かれる一瞬前、目元が淡くきらめいたのが見えたから。
「悪いこはね、なんかいつもと違えなって思ったから。メイクしてんだな」
疑問が解決したからと手元のセトリに戻そうとした意識は、テンションの高い声に引き戻される。
「そう! かわいいでしょ!? さっきあんたたちが来る前に二人でメイクしあってたんだよねー!」
横から抱きついた杏がこはねに頬を寄せる。並んだのを見れば、確かに似たようなパール感の色違いをまぶたに乗せているのがわかる。
いわく、どこかのアイシャドウの限定色がこはねに似合いそうで、しかもパッケージがハムスターイメージときて、どうしてもこはねに使いたくなったらしい。
「昼休みに瑞希が見せてくれたんだけどさ、私に似合いそうなのもあるって言うから。だったらお互いにやりたいなって。ねーこはね?」
「うん、人気だって聞いたから手に入らないかと思ったけど、近くで買えてよかった。フォトコンテストのときの青柳くんと遥ちゃんを見てたから、私もちょっとやってみたかったんだ」
こはねの言葉にオレの隣の冬弥が小さく微笑む。
「そう言ってもらえるのは嬉しいな。……しかしそうか、暁山が楽しそうに白石に会いに行くと言っていたのはそれだったのか」
なるほど、と冬弥が頷く。あいつ確かに今日は昼からいたな。学校来る目的が勉強じゃねえのかよ。自分も勉強は好きじゃないことを棚に上げて考えていると、杏が妙なことを言いだした。
「でさ、さっき話してたんだけど。そのうちイベント出るとき四人でメイクしてみない?」
「……は?」
何言ってんだこいつは。反射的に声に出た。
「限定品とかって色々コンセプトあるでしょ? イベントとか曲のイメージに合ったときとかさ、意識してみるのもいいんじゃないかなって!」
楽しそうな提案の途中、オレははっと気付いて隣を伺う。何せ、そこにいるのは好奇心の塊なのだ。果たして。
「それはとても興味深いな……!」
オレは頭を抱えそうになった。
わかってた、こういうヤツだ。オレの相棒は、初めての経験に興味津々だった。こうなったらもう、アレだ。ほら、俯いたオレを冬弥がチラチラ見ている。わかってるよ、オレはお前に弱いんだ。だから、
「彰人……駄目、だろうか……」
***
つーわけで、やるとなったら中途半端は性に合わねえ。オレらも有名になってきたし、ナメられないためにも見た目も強くしておくのも悪い手じゃないだろう。もちろん、一番は歌でわからせてやることだが。
幸いウチには姉貴の私物っつー参考資料もあるし、メイクは専門外でもコーディネートにはそれなりに自信もある。目的に合わせて演出するって意味じゃ考え方は近いはずだ。
オレが選んだ服、あの白い肌、綺麗な顔の作りを活かすなら。
「よし、やるぞ」
ベッドに座らせた冬弥の前、オレはアイシャドウブラシを構えていた。
「よろしく頼む……?」
冬弥はどこか戸惑っている。最初渋りそうだったオレがここまでやる気になったらそうなっても当たり前だろうが。オレは横に置いたパレットを確認して、冬弥に向き直る。
下地はすでに塗らせた。っつっても、こいつの肌は白くてきめ細やかで、必要ねーんじゃねーかってくらい綺麗だ。
「んじゃ、触るぞ」
一言落として、冬弥の頬に手を添える。下から覗き込んだ相棒の表情が変わった。目を伏せる一瞬、多分オレしか気付かない、ほんのわずかな色。
――そういうことかよ。ほんのひとしずく未満のさみしそうな瞳に、オレは何度呼んだか知れない名前を口にした。
「とーや」
ブラシを当てようとした手を下ろして、ひとつ息を吐き出す。
「別に、お前のメイクが駄目ってわけじゃねーからな」
「……え」
開かれたアイスグレーがオレを見る。そんなん、当たり前だろーが。
そもそも、こいつは自分でしたメイクでフォトコンテストに入賞したんだ。冬弥の表情はもちろん、こはねの写真も良かったにしても、メイクの協力者はあの桐谷だ。オレにあのトレーニングメニューを組んできた桐谷の教え方で、この勉強熱心な真面目バカが取り組んだらどうなるか。写真を見てなくたって、質がいいものになるのはわかりきっている。
「まぁ、専門外のオレがどうこう言えたもんじゃねえけど。でも桐谷にも暁山にも褒められたんだろ。そのお前のメイクが良くなかったわけあるかよ」
そこまで言い切ると、冬弥は顎に手を添えて首を傾げた。
「……では、なぜ彰人は俺にメイクをしてくれようとしているんだ?」
「そんなもん決まってんだろ」
本当にこいつはオレがメイクにもの申すためにやろうとしてたと思ってたんだろうか。理由なんて、その他にいくらでもある。
「メイクってのも要するに外見をどう見せるかって話だからな、ある意味コーディネートの延長線上みたいなもんだ。で、お前の服選んでんのはオレだろ。それなら無関係でいたくねえ」
だから、オレも冬弥のメイクをしてみたかった。まっすぐに冬弥の目を見て言う。
「……っつっても、さっきも言ったが、少しは調べはしたがオレはメイクは専門外だからな。実際自分であんだけやったお前よりはできねえと思う。なんかちげーなとか嫌だなって思ったら容赦なく言えよ。お前に我慢させてまでやりたいわけじゃねえから」
頼りにしてるぞ、相棒。オレの言葉を受け止めた冬弥は、目に見えて嬉しそうに表情を輝かせる。
「そう言ってくれるなら、彰人に任せよう。出来上がりを楽しみにしている」
「ん。じゃあ目ぇ瞑れよ」
ああ。小さな相槌のあと、銀色が見えなくなって、長いまつげの影が落ちる。そっと、白い頬に手を添える。
コーディネートの延長線上、だから無関係でいたくない。冬弥に言ったことは本当だ。だけど、それだけでもない。
冬弥は綺麗だ。本人に自覚はなさそうだが学校でもモテてるし、イベントに来てくれるファンの中にだって容姿を見てるヤツらはいる。ましてあんなコンテストに入賞して、メイクでもっと綺麗になることも、それが評価されることも証明されてしまっている。
その冬弥がメイクをするっていうなら。もっと綺麗になるなら、それで注目を浴びるなら。その冬弥はオレが手を加えた冬弥であって欲しい。冬弥をより魅力的にしたのはオレだって、こいつを見るヤツら全員に思い知らせてやりたい。歌やコーディネート以外のことでも、ぜんぶ。
冬弥は目を閉じて、オレに頬を触らせている。全幅の信頼だ。お前の相棒がこんなどろどろしたもんを抱えてて、何されてもおかしくない状況だってのも知らずに。
艶やかな唇に親指を近付けて、結局触れずに頬に添えた。
「……そういえば、お互いにメイクをしたと、白石は言っていたな」
「ん? ああ、そうだったか」
発端となった日のことだろう。確かにそんなことを言っていた気がする。
「なら、彰人のメイクは俺がしたい」
「……は」
今度こそ冬弥の頬に色を乗せようとしていた手が止まる。それを気配で感じたのか、冬弥が目を開ける。至近距離、きらきら揺れるアイスグレー。
「歌うときの彰人はとてもかっこいいから。彰人も認めてくれた俺のメイクで、彰人をもっと魅力的にすることができるなら、気分がいいだろうと思ったんだ」
そんなことを、楽しくて仕方ないって微笑みで口にするから。
「……おー。んじゃ頼むわ」
「任せてくれ。……すまない、邪魔をしたな。続きをしてくれ」
ふたたび目を閉じた冬弥は、さっきより機嫌が良い。ブラシを持った手に冬弥の息がかかって、距離の近さに今更気付いて唾を飲み込む。
冬弥にメイクされるってことは、目閉じたオレの至近距離にこいつの顔があるってことだよな。そのときの自分がどうなっているのかを少し不安に思いつつ、オレはメイクすることへ意識を向け直した。
3525文字, 2025.06.22 10:00 ss
それは合図になる
#akty
「っし、こんなもんか」
俺の髪に触れていたあたたかい手が離れる。ローテーブルに置いた鏡に映る俺の髪は、右側を編みこまれて項のところでまとめた形に整えられていた。後ろには満足そうな顔をした俺の恋人。
「ありがとう、彰人。出掛ける前にすまない」
「オレが冬弥に触りたくてやってんの」
ぽん、セットしたばかりの髪型を崩さない程度に頭を撫でられ、そのやさしさと言葉に込められた熱に面映ゆい想いがあふれる。道具を片付ける音を聞きながら、編みこまれた髪に触れる。丁寧に施された凹凸を感じて、ほうっと息を吐く。
「俺も触れられるのは嬉しい」
そう落とした直後、不意に感じた衝撃と温度、視界に映るオレンジ色。気付けば俺は彰人の腕の中にいた。後ろから肩に顎を乗せられ、視線は鏡越しに鶸色に絡めとられる。
「急にどうしたんだ」
胸元に回された腕に触れながら言うと、彰人は俺に頭を摺り寄せてくる。
「エロい顔してた」
「っ……」
耳元で紡がれる、低く落とされた声。朝に似つかわしくないそれに囚われてしまいそうで、腕から逃れようと身を捩る。たくましい腕は、当然のように俺を離してはくれない。
「なぁ冬弥、なんで?」
「それは…彰人に触れられたら多少は」
「嘘つけ、今『バレた』って顔したろ。……何考えてた?」
いつも俺を熱くさせる声が、俺を追い詰めるためだけに落とされる。本当に自覚はなかった、それでも、今はしたない顔をしてしまっていたとしたら。
「……整えられた髪が崩れる時のことを考えていた」
伝えてしまってから、頬が熱を持つ。俺の髪が解かれるのは、その大きな熱い手によってに他ならない。この綺麗な編み込みも、そうやって崩されるのかと考えてしまった。
例えば、口を塞がれながら頭を掴まれた時。押し付けられたソファやベッドに擦れた時。項に下りた手が髪留めを外して、編み込みごと手櫛で撫でられた時。それらが何に至る行動か、当の彰人にわからないはずがない。
「っはーーーーー……………」
長く吐き出された吐息が髪を揺らす。彰人の頭がずるずると動き、気付けば額を肩にこすりつけられていた。相棒の行動が読めない俺は戸惑うことしかできない。
「……よし」
何か決意を感じる声と同時に顔が持ち上がった、かと思えば、彰人の手は丁寧に俺の髪をほどき始める。手櫛でゆるめられた編み込みにはしっかりと櫛が通され、青色は元のまっすぐな状態へと戻った。
「彰人、そろそろ出掛ける時間じゃ、」
「いーから座ってろ」
器用な指先は先ほどと同じように俺の頭の側面に編み込みを作っていく。同じことをするのなら何故解いたのだろう、そう考える間に編み込みを終えた手は、今度は反対側にも編み込みを作っていく。
「彰人?」
名前を呼んでも反応はなく、俺の頭にはどんどん編み込みが作られていく。両側から編まれたそれは後ろに残してあったらしい束と合わせてまとめられ、先ほどまでと同じように項で留められた。
「うし、できた。んじゃ行くな」
「あ、あきと」
俺の髪をいじり終えた彰人は横に置いていたバッグを肩に掛け、さっさと玄関に向かってしまう。少し遅れて立ち上がった俺が追いついた時には、彰人は靴を履いてつま先を鳴らしているところだった。俺が前に立ったことに気付くと、顔を上げて鶸色がこちらを見る。伸びてきた手が先ほどまではなかった編み込みに触れる。
「それ。両側に作ったから、見える回数増えるだろ」
崩されること考えるっつーなら。
洗濯機の横の洗面台で。風呂掃除するときに洗い場で。買い出し行った先のショーウインドウで。今までの倍、見えるようになるから。
「意識しろよ。そんで」
帰ったらじっくり崩してやるから、覚悟しとけ。
「……そのつもりなかったとか、言わねえよな?」
耳元に直接注がれた声は湿り気を帯びている。それに弱いことをわかってやっているのだから、俺の恋人は意地が悪い。そんなところまでかっこいいと思ってしまうのだから、心底惚れているのだと改めて感じてしまう。
「……待っている」
それだけ告げると、目の前の彰人は不自然に口を開いたあと、何かを堪えるように目と口を同時に閉じた。 頭の後ろをがしがしとしてから、鶸色が俺をねめつける。
「ほんっと覚えとけよ」
その言葉を最後に俺に背を向けた彰人は、いつもより少し乱暴に玄関の扉を閉めて出て行った。手を伸ばして鍵を閉めて、ふと玄関横の姿見に映る自分の姿に気が付く。いつもと反対側に見える編み込み。
「……本当に、ずっと意識してしまうな」
胸を満たす幸せな甘さは、焦がれる人の名前となって唇から零れ落ちた。
#akty
「っし、こんなもんか」
俺の髪に触れていたあたたかい手が離れる。ローテーブルに置いた鏡に映る俺の髪は、右側を編みこまれて項のところでまとめた形に整えられていた。後ろには満足そうな顔をした俺の恋人。
「ありがとう、彰人。出掛ける前にすまない」
「オレが冬弥に触りたくてやってんの」
ぽん、セットしたばかりの髪型を崩さない程度に頭を撫でられ、そのやさしさと言葉に込められた熱に面映ゆい想いがあふれる。道具を片付ける音を聞きながら、編みこまれた髪に触れる。丁寧に施された凹凸を感じて、ほうっと息を吐く。
「俺も触れられるのは嬉しい」
そう落とした直後、不意に感じた衝撃と温度、視界に映るオレンジ色。気付けば俺は彰人の腕の中にいた。後ろから肩に顎を乗せられ、視線は鏡越しに鶸色に絡めとられる。
「急にどうしたんだ」
胸元に回された腕に触れながら言うと、彰人は俺に頭を摺り寄せてくる。
「エロい顔してた」
「っ……」
耳元で紡がれる、低く落とされた声。朝に似つかわしくないそれに囚われてしまいそうで、腕から逃れようと身を捩る。たくましい腕は、当然のように俺を離してはくれない。
「なぁ冬弥、なんで?」
「それは…彰人に触れられたら多少は」
「嘘つけ、今『バレた』って顔したろ。……何考えてた?」
いつも俺を熱くさせる声が、俺を追い詰めるためだけに落とされる。本当に自覚はなかった、それでも、今はしたない顔をしてしまっていたとしたら。
「……整えられた髪が崩れる時のことを考えていた」
伝えてしまってから、頬が熱を持つ。俺の髪が解かれるのは、その大きな熱い手によってに他ならない。この綺麗な編み込みも、そうやって崩されるのかと考えてしまった。
例えば、口を塞がれながら頭を掴まれた時。押し付けられたソファやベッドに擦れた時。項に下りた手が髪留めを外して、編み込みごと手櫛で撫でられた時。それらが何に至る行動か、当の彰人にわからないはずがない。
「っはーーーーー……………」
長く吐き出された吐息が髪を揺らす。彰人の頭がずるずると動き、気付けば額を肩にこすりつけられていた。相棒の行動が読めない俺は戸惑うことしかできない。
「……よし」
何か決意を感じる声と同時に顔が持ち上がった、かと思えば、彰人の手は丁寧に俺の髪をほどき始める。手櫛でゆるめられた編み込みにはしっかりと櫛が通され、青色は元のまっすぐな状態へと戻った。
「彰人、そろそろ出掛ける時間じゃ、」
「いーから座ってろ」
器用な指先は先ほどと同じように俺の頭の側面に編み込みを作っていく。同じことをするのなら何故解いたのだろう、そう考える間に編み込みを終えた手は、今度は反対側にも編み込みを作っていく。
「彰人?」
名前を呼んでも反応はなく、俺の頭にはどんどん編み込みが作られていく。両側から編まれたそれは後ろに残してあったらしい束と合わせてまとめられ、先ほどまでと同じように項で留められた。
「うし、できた。んじゃ行くな」
「あ、あきと」
俺の髪をいじり終えた彰人は横に置いていたバッグを肩に掛け、さっさと玄関に向かってしまう。少し遅れて立ち上がった俺が追いついた時には、彰人は靴を履いてつま先を鳴らしているところだった。俺が前に立ったことに気付くと、顔を上げて鶸色がこちらを見る。伸びてきた手が先ほどまではなかった編み込みに触れる。
「それ。両側に作ったから、見える回数増えるだろ」
崩されること考えるっつーなら。
洗濯機の横の洗面台で。風呂掃除するときに洗い場で。買い出し行った先のショーウインドウで。今までの倍、見えるようになるから。
「意識しろよ。そんで」
帰ったらじっくり崩してやるから、覚悟しとけ。
「……そのつもりなかったとか、言わねえよな?」
耳元に直接注がれた声は湿り気を帯びている。それに弱いことをわかってやっているのだから、俺の恋人は意地が悪い。そんなところまでかっこいいと思ってしまうのだから、心底惚れているのだと改めて感じてしまう。
「……待っている」
それだけ告げると、目の前の彰人は不自然に口を開いたあと、何かを堪えるように目と口を同時に閉じた。 頭の後ろをがしがしとしてから、鶸色が俺をねめつける。
「ほんっと覚えとけよ」
その言葉を最後に俺に背を向けた彰人は、いつもより少し乱暴に玄関の扉を閉めて出て行った。手を伸ばして鍵を閉めて、ふと玄関横の姿見に映る自分の姿に気が付く。いつもと反対側に見える編み込み。
「……本当に、ずっと意識してしまうな」
胸を満たす幸せな甘さは、焦がれる人の名前となって唇から零れ落ちた。
1971文字, 2025.06.22 10:00 ss
背に流る青の所以
#akty
その日届いた献本に載っていたのは、オレたちが高校生のころからの軌跡を辿った特集だった。四人の写真はもちろん、三田や遠野と写った写真、冬弥と二人の写真もある。練習風景のそれは当時こはねが撮ったものだと一文が添えられていた。
幼さの残る自分たちを眺めて、それから隣に目をやる。同じソファに腰掛け一緒に雑誌を覗く相棒の髪型は、写真のそれとは異なっている。
「髪、ずいぶん伸びたな」
さらり。項で結われ、背中に流れる青色を掬い取る。オレの手に気付いた冬弥は、ああ、と反対側から自分の髪に触れた。どこか感慨深そうに、指先で髪を梳く。
「……実を言うと、丁度この頃からなんだ。髪を伸ばそうと考えたのは」
「へぇ」
誌面の写真を指さしながら言う。傍らに並ぶ文字は「RAD BLAST」。オレたちが伝説を超えたイベントだ。
「っつーことは高二か。結構前から考えてたんだな」
言われてみれば、高校を卒業してルームシェアをするようになった頃には冬弥の髪は結べる長さだった。服のコーディネートだけじゃなく、毎朝のスタイリングもやってやるようになった時のことをよく覚えている。まっすぐで艶やかな長い髪に触れて、オレの手で変わっていく様を見るのは楽しかった。
冬弥がどこか困ったように眉を下げるのが見えて、眉が寄りそうになったのをなんとか抑える。気付いたことを悟られたくはない。――今の流れで、なんでそんな顔すんだよ。
雑誌を閉じてテーブルに置く。相棒の様子に気を掛けようと姿勢を変えた時、そっと言葉が落とされた。
「……願掛けだった、と言ったら、驚くだろうか」
願掛け。たぶん、髪を伸ばしていたのが。冬弥が。数秒かけてそう認識して、すぐには声が出なかった。
「やはり、驚いているな」
「驚いてるっつーか……まぁ、欲しいもんは自力で、ってヤツだと思ってたのはあるが」
「彰人と一緒にいれば誰でもそうなる」
彰人と一緒だったから、俺はなりたい自分になれた。やわらかい笑顔で言われて、さっきとは別の意味で虚をつかれる。……本当に、こいつはこれだから。
小さく声を上げて笑う冬弥はいつもの冬弥だったが、またさっきと似た表情になる。困ったような――あるいは、何かを抑えるような。
「叶えるなら自分の力で。そう思うことが多いのは事実だ。だけど、こればかりは、俺だけの力でどうにかなるものではないから。……それに、そろそろ切ろうかと思っている。」
「……ふーん、イメチェン?だいぶ変わるが、いいんじゃねぇか。ただ、短くしたらあんまアレンジしてやれなくなるな。お前の髪いじるの、けっこう好きだったんだけどな」
無理に聞き出したくはないから、軽く返す。冬弥は目を閉じて、一層複雑そうな顔をした。
「そういう理由ではないんだ。そうだな――例えば、恋愛小説で。髪を切る理由なんて、いくつもないだろう?」
「――は?」
恋愛小説なんてものを好んで読んだことがないオレだが、冬弥が何を言っているのかわからないほど物知らずでもない。つまり。
(……失恋)
――一瞬、意識が飛んでいたような気がする。要するに、オレはそれほどの衝撃を受けたということらしい。相棒の今の発言に。
冬弥に、そんな相手がいたなんて知らなかった。気付かなかった。長年一番近くにいたのに。
当然、冬弥が気付かせようとしなかったからだろう。そんな話があれば相談してもらえると自惚れていたことに気付いて、そうやって知らせてもらえなかったことにショックを受けている自分の傲慢さも嫌になった。
何も紡げず口を開いたままのオレを一瞥した冬弥は、それからそっと空を見つめた。
「元々、期間を決めていたんだ。三年。それを過ぎたら諦めようと。RADWEEKENDを超えて、少しだけ自分の望みに心を向けてもいいんじゃないかと思って、願いを掛け始めた。世界を志すのを甘くみたわけじゃない。それでも、ひとつのきっかけとして。賭けてみたくなったんだ」
オレは滔々と紡がれる声を聞くことしかできない。くるくると長い髪を指に巻き付けながら冬弥は続ける。願いを込めて、髪を伸ばし始めた。けれど。
「少し疲れてしまったのもある。……実を言うと、勝算はあると思っていた。その人にとって、自分は特別な存在だと。そこまでは、自惚れではないと思う。だが」
その人は俺が望む瞳で、俺を見てはくれないから。
――だから。
その先を口にしようとした冬弥の動きが止まる。自分の髪をもてあそぶ手を、オレが掴んだからだ。アイスグレーの視線が注がれるのを感じながら、その長い髪を見つめる。
「……そんな見る目ねえヤツのために、この髪切っちまうのかよ」
冬弥の誠実さと純粋さをそのまま映したみたいな、細やかで美しい髪。それを、冬弥が寄せる気持ちに気付きもしない、熱くて清廉で夢に本気で音楽が好きでクソ真面目で努力家で危なっかしくてほっとけない冬弥のことを何もわかっちゃいないどこの誰だかも知れないバカのために切り落とすつもりだという。
オレに口出しする資格がないことくらいわかっている。それでも。
そんな冬弥そのものみたいなきらきらしたものを、冬弥のやわらかい想いごと踏みにじるようなヤツにくれてやるくらいなら。
どろり、めらり。自分の中で何かが揺れて、噴き上がるのがわかる。
それなら、あの日鍵をかけて墓まで持って行くと決めて奥底に沈めた身勝手な欲を、いっそ、
(……駄目だ)
「……悪い、」
掴んだままだった冬弥の手を開放する。目を瞑って深呼吸、ほんの少し噴き出してしまった醜い感情を封じ込め直す。大きく息を吐き出して、顔を上げて、冬弥に向き直ろうとして、
「……は」
オレは言葉を失った。目に入ったものが、あまりに想定外だったからだ。
冬弥は白い肌を微かに赤く染め、熱を湛えた瞳でオレを見ていた。ぶん殴られたみたいに頭が揺さぶられて、たった今押し込めたそれが顔を出したがるのを蹴り飛ばす。
「……どうして、今更そんな目で俺を見るんだ」
オレの耳に流れ込んでくる聞いたことがないくらいに艶っぽい声は、本当に冬弥のものだろうか。もっと全身で聞きたいと思うのに、聞こえないくらいに自分の心臓の音がうるさい。
「……どんな目だよ」
問い返した自分の声も、信じられないくらいにかすれている。それに何かを感じ取ったのか、冬弥は戸惑いと期待の入り混じったような表情で口を開く。
「何もかも焼き尽くす、炎のような、瞳」
艶やかな髪が絡まったままの白い手がオレの頬に添えられた。陶酔とすら言えそうな溶けたアイスグレーに捕えられる。
――冬弥はいつからこんな顔をしていた?こんな目でオレを見ていた?今急にでないのなら、変わったのはオレの意識、蓋を開けてしまった感情だけだ。長い間追いやっていたそれを通してみれば、静かな熱はこんなにもわかりやすい。
無意識のうちに自分の喉が鳴る。自然、引き寄せられながら、シルバーグレーが瞼に隠されていくのを見た。
……ああもう、バカはどいつだよ。
***
「……で?」
シーツに散らばる汗ばんだ髪をもてあそびながら傍らに問う。
「切っちまうの、これ」
「そうだな……」
願掛けの意味を考えると切ってもいいんだが。
「……」
「俺がずっと好きだった……いや、これからもずっと好きな人が。俺の髪に触れたり乾かしたり整えたりセットしたりするのが好きなようだから。それに、俺も触れられるのが好きだから。このままにしておく」
「……そーかよ」
#akty
その日届いた献本に載っていたのは、オレたちが高校生のころからの軌跡を辿った特集だった。四人の写真はもちろん、三田や遠野と写った写真、冬弥と二人の写真もある。練習風景のそれは当時こはねが撮ったものだと一文が添えられていた。
幼さの残る自分たちを眺めて、それから隣に目をやる。同じソファに腰掛け一緒に雑誌を覗く相棒の髪型は、写真のそれとは異なっている。
「髪、ずいぶん伸びたな」
さらり。項で結われ、背中に流れる青色を掬い取る。オレの手に気付いた冬弥は、ああ、と反対側から自分の髪に触れた。どこか感慨深そうに、指先で髪を梳く。
「……実を言うと、丁度この頃からなんだ。髪を伸ばそうと考えたのは」
「へぇ」
誌面の写真を指さしながら言う。傍らに並ぶ文字は「RAD BLAST」。オレたちが伝説を超えたイベントだ。
「っつーことは高二か。結構前から考えてたんだな」
言われてみれば、高校を卒業してルームシェアをするようになった頃には冬弥の髪は結べる長さだった。服のコーディネートだけじゃなく、毎朝のスタイリングもやってやるようになった時のことをよく覚えている。まっすぐで艶やかな長い髪に触れて、オレの手で変わっていく様を見るのは楽しかった。
冬弥がどこか困ったように眉を下げるのが見えて、眉が寄りそうになったのをなんとか抑える。気付いたことを悟られたくはない。――今の流れで、なんでそんな顔すんだよ。
雑誌を閉じてテーブルに置く。相棒の様子に気を掛けようと姿勢を変えた時、そっと言葉が落とされた。
「……願掛けだった、と言ったら、驚くだろうか」
願掛け。たぶん、髪を伸ばしていたのが。冬弥が。数秒かけてそう認識して、すぐには声が出なかった。
「やはり、驚いているな」
「驚いてるっつーか……まぁ、欲しいもんは自力で、ってヤツだと思ってたのはあるが」
「彰人と一緒にいれば誰でもそうなる」
彰人と一緒だったから、俺はなりたい自分になれた。やわらかい笑顔で言われて、さっきとは別の意味で虚をつかれる。……本当に、こいつはこれだから。
小さく声を上げて笑う冬弥はいつもの冬弥だったが、またさっきと似た表情になる。困ったような――あるいは、何かを抑えるような。
「叶えるなら自分の力で。そう思うことが多いのは事実だ。だけど、こればかりは、俺だけの力でどうにかなるものではないから。……それに、そろそろ切ろうかと思っている。」
「……ふーん、イメチェン?だいぶ変わるが、いいんじゃねぇか。ただ、短くしたらあんまアレンジしてやれなくなるな。お前の髪いじるの、けっこう好きだったんだけどな」
無理に聞き出したくはないから、軽く返す。冬弥は目を閉じて、一層複雑そうな顔をした。
「そういう理由ではないんだ。そうだな――例えば、恋愛小説で。髪を切る理由なんて、いくつもないだろう?」
「――は?」
恋愛小説なんてものを好んで読んだことがないオレだが、冬弥が何を言っているのかわからないほど物知らずでもない。つまり。
(……失恋)
――一瞬、意識が飛んでいたような気がする。要するに、オレはそれほどの衝撃を受けたということらしい。相棒の今の発言に。
冬弥に、そんな相手がいたなんて知らなかった。気付かなかった。長年一番近くにいたのに。
当然、冬弥が気付かせようとしなかったからだろう。そんな話があれば相談してもらえると自惚れていたことに気付いて、そうやって知らせてもらえなかったことにショックを受けている自分の傲慢さも嫌になった。
何も紡げず口を開いたままのオレを一瞥した冬弥は、それからそっと空を見つめた。
「元々、期間を決めていたんだ。三年。それを過ぎたら諦めようと。RADWEEKENDを超えて、少しだけ自分の望みに心を向けてもいいんじゃないかと思って、願いを掛け始めた。世界を志すのを甘くみたわけじゃない。それでも、ひとつのきっかけとして。賭けてみたくなったんだ」
オレは滔々と紡がれる声を聞くことしかできない。くるくると長い髪を指に巻き付けながら冬弥は続ける。願いを込めて、髪を伸ばし始めた。けれど。
「少し疲れてしまったのもある。……実を言うと、勝算はあると思っていた。その人にとって、自分は特別な存在だと。そこまでは、自惚れではないと思う。だが」
その人は俺が望む瞳で、俺を見てはくれないから。
――だから。
その先を口にしようとした冬弥の動きが止まる。自分の髪をもてあそぶ手を、オレが掴んだからだ。アイスグレーの視線が注がれるのを感じながら、その長い髪を見つめる。
「……そんな見る目ねえヤツのために、この髪切っちまうのかよ」
冬弥の誠実さと純粋さをそのまま映したみたいな、細やかで美しい髪。それを、冬弥が寄せる気持ちに気付きもしない、熱くて清廉で夢に本気で音楽が好きでクソ真面目で努力家で危なっかしくてほっとけない冬弥のことを何もわかっちゃいないどこの誰だかも知れないバカのために切り落とすつもりだという。
オレに口出しする資格がないことくらいわかっている。それでも。
そんな冬弥そのものみたいなきらきらしたものを、冬弥のやわらかい想いごと踏みにじるようなヤツにくれてやるくらいなら。
どろり、めらり。自分の中で何かが揺れて、噴き上がるのがわかる。
それなら、あの日鍵をかけて墓まで持って行くと決めて奥底に沈めた身勝手な欲を、いっそ、
(……駄目だ)
「……悪い、」
掴んだままだった冬弥の手を開放する。目を瞑って深呼吸、ほんの少し噴き出してしまった醜い感情を封じ込め直す。大きく息を吐き出して、顔を上げて、冬弥に向き直ろうとして、
「……は」
オレは言葉を失った。目に入ったものが、あまりに想定外だったからだ。
冬弥は白い肌を微かに赤く染め、熱を湛えた瞳でオレを見ていた。ぶん殴られたみたいに頭が揺さぶられて、たった今押し込めたそれが顔を出したがるのを蹴り飛ばす。
「……どうして、今更そんな目で俺を見るんだ」
オレの耳に流れ込んでくる聞いたことがないくらいに艶っぽい声は、本当に冬弥のものだろうか。もっと全身で聞きたいと思うのに、聞こえないくらいに自分の心臓の音がうるさい。
「……どんな目だよ」
問い返した自分の声も、信じられないくらいにかすれている。それに何かを感じ取ったのか、冬弥は戸惑いと期待の入り混じったような表情で口を開く。
「何もかも焼き尽くす、炎のような、瞳」
艶やかな髪が絡まったままの白い手がオレの頬に添えられた。陶酔とすら言えそうな溶けたアイスグレーに捕えられる。
――冬弥はいつからこんな顔をしていた?こんな目でオレを見ていた?今急にでないのなら、変わったのはオレの意識、蓋を開けてしまった感情だけだ。長い間追いやっていたそれを通してみれば、静かな熱はこんなにもわかりやすい。
無意識のうちに自分の喉が鳴る。自然、引き寄せられながら、シルバーグレーが瞼に隠されていくのを見た。
……ああもう、バカはどいつだよ。
***
「……で?」
シーツに散らばる汗ばんだ髪をもてあそびながら傍らに問う。
「切っちまうの、これ」
「そうだな……」
願掛けの意味を考えると切ってもいいんだが。
「……」
「俺がずっと好きだった……いや、これからもずっと好きな人が。俺の髪に触れたり乾かしたり整えたりセットしたりするのが好きなようだから。それに、俺も触れられるのが好きだから。このままにしておく」
「……そーかよ」
3152文字, 2025.06.22 10:00 ss
彰冬習作
#akty
※成人済、こはね視点、彰人不在、杏こは杏
※彰冬と言い張る
***
もう夜も更けた時間、杏ちゃんに呼ばれたお店で私が見たのは、楽しそうに向かいを見つめる杏ちゃんと、ふわふわと東雲くんの話をする青柳くんの姿だった。
先月のイベントで知り合った人たちに誘われた打ち上げ。次のイベントの準備もある時期だったけど、RADerやクラシックも好きだという彼らの希望があったから、杏ちゃんと青柳くんの二人だけで参加して、その日の準備は私と東雲くんで進めることになった。
杏ちゃんから連絡をもらったのは夜の九時過ぎ。その打ち上げがいったんお開きになって、二人だけで別のお店に入ったから、作業が落ち着いてたら会いたい、というお誘いで、もちろん快諾した。東雲くんは車で遠出をしてたから、私は先に二人と合流することにした、んだけど。
「杏ちゃん……もしかして、青柳くん、結構酔ってる?」
みんなでよく来るお店の個室、杏ちゃんの隣に座りながら尋ねる。杏ちゃんの向かいに座る青柳くんは、いつも飲むときより赤い顔をしていて、どこかふわふわした雰囲気だ。そう、東雲くんと二人でいるときみたいな。
私の注文のためにだろう、杏ちゃんは店員さんを呼ぶボタンを押しながら答えてくれる。
「冬弥のお父さんに会ったことある人だったみたいでさ。すごい楽しそうに話聞いてるうちに結構飲んでたみたい。目上の人と一緒だったのもあってあんまり顔には出てなかったけど、ちょっと危ないかなー?って思って、二次会は辞退してきたんだ」
慣れたとこで気が抜けたのかな、ここ来てからふにゃってなっちゃった。杏ちゃんの話に頷きつつ、来てくれた店員さんにお湯割りをお願いする。それから、ななめ前の青柳くんを見つめる。私に気付いた彼は、きれいなアイスグレーに私を映して笑った。
「……小豆沢。小豆沢も聞いてくれ、彰人がかっこいいんだ」
「……え?」
普段より上機嫌な声が語るのは、彼の相棒の話だった。イベントで隣に立ったときの姿や歌声、練習しているときの熱心な様子。淀みなく、絶えることなく紡がれる事柄のほとんどは、私たちも高校生のころからよく知っている東雲くんの美点たち。
「さっきからずーっとこう」
ずーっと彰人がかっこいいって話してて、しかも全部違う話なの。杏ちゃんがテーブルの上に置いたスマホに触れながら言う。その表情は落ち着いていて、冷やかすとか呆れたとか、そんな感情は見えない。でも確かに、青柳くんはお酒に強い方だから、私もここまで酔ったのを見たのは初めてだけど。結構予想通り、かも。
私はグラスを傾けながら頷く。
「ふふ、わかるよ。東雲くん、かっこいいよね」
「そうか、わかってくれるか小豆沢」
「ええ~こはね私はぁ~?」
今度は杏ちゃんが私の話をしはじめた。ちょっと恥ずかしくて、でも嬉しい。杏ちゃんはいつも私のことを褒めてくれるけど、いつもよりもっと饒舌な気がする。やっぱり杏ちゃんも酔ってるみたい。
「こはねぇ~……」
「ありがとう、杏ちゃん。私もかっこよくて可愛い杏ちゃんのこと、大好きだよ」
「こはねぇ~~!!」
抱きついてくる杏ちゃんを受け止める。杏ちゃんは私を抱き寄せる腕を強めながら、青柳くんを指さした。
「どーだ冬弥、こはねはかっこいいし、それにこーんなに可愛いんだから! 彰人じゃこうはいかないでしょ!」
「杏ちゃん……」
頬ずりしてくる杏ちゃんの背中をゆるくさする。青柳くんは突然の勝利宣言に一瞬呆けた顔をしたけれど、その表情はすぐにやわらかくくずれた。
「……そうかもしれない。彰人も二人を含む身内の前では素直だけれど、それでも格好をつけたがるところがあるから」
だけど。
「俺にだけ見せてくれる彰人は、とても可愛らしくて、愛おしいと、そう思う」
そんな彰人が好きだ。
――まるで、花が咲いたような、お砂糖を煮詰めたみたいな。今日見た中でも、とびきりの甘い表情で、青柳くんが笑うから。
お裾分けをもらったみたいで、私も幸せな気持ちになってしまって。
「――うん」
一生大事にしよう。何百回目の決意をして、まどろみ始めた杏ちゃんを抱きしめた。
***
「ねーこはね、この前冬弥がめちゃくちゃ惚気てたときあったでしょ」
「あ、杏ちゃんと青柳くんが先にいつものお店にいたときのこと?」
「そうそう。あのとき冬弥の惚気録音してたんだけどさ。あとで彰人に聞かせたら面白い反応見られるかなって思って」
「それで杏ちゃん途中でスマホいじってたんだね」
「うん。で、録音聞いて彰人のやつ何て言ったと思う?」
「……そういう言い方するってことは、杏ちゃんの言う面白い反応、とかじゃなかったんだよね……『知ってる』とか?」
「『ほとんど毎日聞いてる』」
「……え」
「そのときの彰人の顔がさ、仕方ねーな、みたいに見せて、大事ですー好きですーってのをぜんっぜん隠そうともしてなくてさ」
「うん」
「何も言えないじゃん、そんなの」
「うん。……ねぇ、杏ちゃん」
「んー?」
「私も大好きだよ」
#akty
※成人済、こはね視点、彰人不在、杏こは杏
※彰冬と言い張る
***
もう夜も更けた時間、杏ちゃんに呼ばれたお店で私が見たのは、楽しそうに向かいを見つめる杏ちゃんと、ふわふわと東雲くんの話をする青柳くんの姿だった。
先月のイベントで知り合った人たちに誘われた打ち上げ。次のイベントの準備もある時期だったけど、RADerやクラシックも好きだという彼らの希望があったから、杏ちゃんと青柳くんの二人だけで参加して、その日の準備は私と東雲くんで進めることになった。
杏ちゃんから連絡をもらったのは夜の九時過ぎ。その打ち上げがいったんお開きになって、二人だけで別のお店に入ったから、作業が落ち着いてたら会いたい、というお誘いで、もちろん快諾した。東雲くんは車で遠出をしてたから、私は先に二人と合流することにした、んだけど。
「杏ちゃん……もしかして、青柳くん、結構酔ってる?」
みんなでよく来るお店の個室、杏ちゃんの隣に座りながら尋ねる。杏ちゃんの向かいに座る青柳くんは、いつも飲むときより赤い顔をしていて、どこかふわふわした雰囲気だ。そう、東雲くんと二人でいるときみたいな。
私の注文のためにだろう、杏ちゃんは店員さんを呼ぶボタンを押しながら答えてくれる。
「冬弥のお父さんに会ったことある人だったみたいでさ。すごい楽しそうに話聞いてるうちに結構飲んでたみたい。目上の人と一緒だったのもあってあんまり顔には出てなかったけど、ちょっと危ないかなー?って思って、二次会は辞退してきたんだ」
慣れたとこで気が抜けたのかな、ここ来てからふにゃってなっちゃった。杏ちゃんの話に頷きつつ、来てくれた店員さんにお湯割りをお願いする。それから、ななめ前の青柳くんを見つめる。私に気付いた彼は、きれいなアイスグレーに私を映して笑った。
「……小豆沢。小豆沢も聞いてくれ、彰人がかっこいいんだ」
「……え?」
普段より上機嫌な声が語るのは、彼の相棒の話だった。イベントで隣に立ったときの姿や歌声、練習しているときの熱心な様子。淀みなく、絶えることなく紡がれる事柄のほとんどは、私たちも高校生のころからよく知っている東雲くんの美点たち。
「さっきからずーっとこう」
ずーっと彰人がかっこいいって話してて、しかも全部違う話なの。杏ちゃんがテーブルの上に置いたスマホに触れながら言う。その表情は落ち着いていて、冷やかすとか呆れたとか、そんな感情は見えない。でも確かに、青柳くんはお酒に強い方だから、私もここまで酔ったのを見たのは初めてだけど。結構予想通り、かも。
私はグラスを傾けながら頷く。
「ふふ、わかるよ。東雲くん、かっこいいよね」
「そうか、わかってくれるか小豆沢」
「ええ~こはね私はぁ~?」
今度は杏ちゃんが私の話をしはじめた。ちょっと恥ずかしくて、でも嬉しい。杏ちゃんはいつも私のことを褒めてくれるけど、いつもよりもっと饒舌な気がする。やっぱり杏ちゃんも酔ってるみたい。
「こはねぇ~……」
「ありがとう、杏ちゃん。私もかっこよくて可愛い杏ちゃんのこと、大好きだよ」
「こはねぇ~~!!」
抱きついてくる杏ちゃんを受け止める。杏ちゃんは私を抱き寄せる腕を強めながら、青柳くんを指さした。
「どーだ冬弥、こはねはかっこいいし、それにこーんなに可愛いんだから! 彰人じゃこうはいかないでしょ!」
「杏ちゃん……」
頬ずりしてくる杏ちゃんの背中をゆるくさする。青柳くんは突然の勝利宣言に一瞬呆けた顔をしたけれど、その表情はすぐにやわらかくくずれた。
「……そうかもしれない。彰人も二人を含む身内の前では素直だけれど、それでも格好をつけたがるところがあるから」
だけど。
「俺にだけ見せてくれる彰人は、とても可愛らしくて、愛おしいと、そう思う」
そんな彰人が好きだ。
――まるで、花が咲いたような、お砂糖を煮詰めたみたいな。今日見た中でも、とびきりの甘い表情で、青柳くんが笑うから。
お裾分けをもらったみたいで、私も幸せな気持ちになってしまって。
「――うん」
一生大事にしよう。何百回目の決意をして、まどろみ始めた杏ちゃんを抱きしめた。
***
「ねーこはね、この前冬弥がめちゃくちゃ惚気てたときあったでしょ」
「あ、杏ちゃんと青柳くんが先にいつものお店にいたときのこと?」
「そうそう。あのとき冬弥の惚気録音してたんだけどさ。あとで彰人に聞かせたら面白い反応見られるかなって思って」
「それで杏ちゃん途中でスマホいじってたんだね」
「うん。で、録音聞いて彰人のやつ何て言ったと思う?」
「……そういう言い方するってことは、杏ちゃんの言う面白い反応、とかじゃなかったんだよね……『知ってる』とか?」
「『ほとんど毎日聞いてる』」
「……え」
「そのときの彰人の顔がさ、仕方ねーな、みたいに見せて、大事ですー好きですーってのをぜんっぜん隠そうともしてなくてさ」
「うん」
「何も言えないじゃん、そんなの」
「うん。……ねぇ、杏ちゃん」
「んー?」
「私も大好きだよ」
2125文字, 2025.05.23 10:00 ss
Powered by てがろぐ Ver 4.7.0.

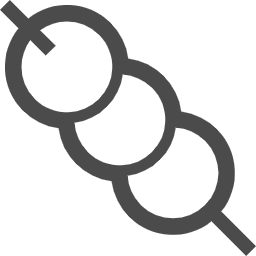
#akty 2025.11.24-26webオンリー初出 Klavierの続き
「せっかくピアノセッテッィングしたんだし、そのジャズバーの練習がてら歌っていきなよ!」
そう言ったのは、どちらのお調子者だったか。
ともかく、件のバーで歌う曲に似たバーチャルシンガー楽曲を奏でられ、あまつさえ挑発するような弾き方さえされたら、歌わないという選択肢なんかなくて。
鍵盤の音色に求められるままに相棒と声を重ねる。目を合わせて頷きあい、乗ってこいと煽る演奏に応える。
転調や曲の移り変わりに歌で返して数曲、不意に音を止めたピアノの奏者の方を見れば、そっと手首を指さしている。壁掛け時計を見ると、長針は思ったより回った場所にあった。
「一旦休憩するか……」
「そうだな……」
軽く腕を回しながらカウンターに戻る。高い椅子に腰を落ち着けると、彰人の目の前にグラスが置かれた。
「おつかれさま! はい、冬弥くん色のカクテル~」
彰人くんも飲めるやつだよ、とルカが差し出してきたのは青から水色、白へのグラデーションが美しいカクテルだった。歌っている間にメイコが用意してくれていたのだろう。冬弥色ってどういうことだと思わなくもなかったが、ありがたくグラスに口を付ける。歌い終わりの身体は一気にグラスの半分ほどを飲み干していた。
「……ん?」
ふと、喉に違和感を覚える。じわじわと熱くなる感じ。これは、まさか。
「あー! ルカ、彰人くんのそれボクのお酒!」
思い切りむせた。つまりこれはアルコールということで。
「……何飲ますんすか!」
「ごめーん気付かなかった~!」
「ボクのお酒~!」
じゃあ青と白はカイトの色だったのか。その事実になんとなく安堵しつつ、わちゃつきだした二人に背を向けた。カウンターについた肘にもたれかかる。
「ったく……」
「お酒を飲んだのか?」
びくり、顔を上げる。冬弥の顔は思ったより近い距離で、じっとりと彰人を見つめていた。
「いや違う、これは事故で。ルカさんに出されたのがカイトさんのカクテルだっただけで」
背後の二人を示しながら弁解する。彰人とその後ろを交互に見た冬弥は、しばらくして再度彰人を見つめてくる。
「……では彰人の意思で飲んだわけではないのだな」
「そう言ってんだろ……そもそも、飲める歳でも進んで飲もうとはしねえと思うぞ」
安堵したまま言いつのれば、相棒はきょと、と首を傾げる。
「……そうなのか?」
「ん? ああ、普段からクラブでも歌わせてもらってるし、バーで歌うのもこれっきりでもねえだろうし、成人したら付き合いでくらい飲むだろうけどよ。わざわざ喉痛めるようなもん自分からは飲まねえだろうなって」
冬弥はどこか少しむっとしている。やはり飲んだことを気にしているのだろうか。
「んだよ……間違えちまったのは仕方ねえだろ」
「いや、事故なのはわかった。それはいいんだ。ただ、少し残念に感じてしまって」
「は?」
「WEEKEND GARAGEで楽しそうにお酒を飲んでいる人たちを見ていたからな。俺も成人したら彰人と一緒に飲むのだと、楽しみにしていたんだが」
彰人は成人後の飲酒に積極的ではないようだし、初めてのお酒も取られてしまったな。
そう言って、少し寂しそうに眉を下げるから。
……ああもうこいつは。
「………………お前と飲みたくないなんて言ってねえだろ……」
好んで日常的に飲むことはしないにしろ、彰人だって気心しれた仲との飲みには興味があるし、酔ってとろけた冬弥を見てみたいという欲もある。
彰人はひとつ息を吐き出すと、グラスに残っていたカクテルを一気に煽った。
「彰人!?」
今のやりとりのあとで明らかに自らアルコールを口にしたことにだろう、冬弥の戸惑いの声が聞こえる。表情には法律違反を咎めようとする色が見える。
その冬弥の顎を掴んで、唇を重ねた。
「んっ……!」
唇を押し開き、煽ったものを流し込む。冬弥の喉が動くのを見てから、今度は薄い舌を引き込んで己の口の中で絡め取る。
「ふ……んむ……」
「……は、」
たっぷり口内を味わって、彰人の腕を叩いていた冬弥の手の力が抜けたころ、唇を離した。俯いて肩を上下させる冬弥を見て、ふっと笑みが零れる。
「……これで共犯。で、オレの初めての酒はお前と一緒だったってわけだ」
だから、これでいいだろ。そう言い落としてずらした視線の先で、店の入り口からこはねと杏、ミクが彰人たちを見ていた。杏とミクはリンとレンの目を塞いでいる。
時間が、止まったみたいだった。
「……おまえら、いつから」
思わず声が零れるが、幼い二人が目を塞がれている事実が見られていたことを物語っている。最中に冬弥が腕を叩いてきていたのも、彰人が夢中で聞こえなかったドアベルの音を優れた彼の耳は捉えていたからだったのかもしれない。
そもそもメイコさんたちがいることはわかっていたはずなのに、何してたんだ、オレ。冷静になってきて頭を抱えた彰人に、杏の声が降ってくる。
「大人三人でバー状態でカフェ独占してるからつまんないーってリンちゃんたちが来たからこはねも誘って一緒に来てみたんだけど」
そこまで言って、ミクに目配せする。何ー?とか離せよー!という黄色い声だけが聞こえる。
「お酒とは別の意味で二人には早かったかなー」
「……ええと、ごゆっくり?」
からんからん、ぱたん。こはねの言葉を最後に、五人は店から姿を消した。彰人の隣で俯いていた冬弥が立ち上がる。
「冬弥?」
「……白石たちに説明してくる」
冬弥は顔を隠したまま、足早に店を出てしまう。からんからん、再度ドアベルが店に鳴り響いた。
「……」
そっと背後を伺うと、青色と桃色はカクテルを混ぜるのに夢中になっている。何も知らないと、そう接してくれるつもりなのだろう。無言の気遣いにどうしようもなくいたたまれなくなる。
ふと、カウンターの向こうに動く影があり、そちらを見る。メイコが透明な液体が入ったグラスを差し出してくる。
「……さっきのカイトのカクテル、ちょっと強いお酒を使ってたみたいだから」
言い訳と共に与えられたグラスを手に取って、匂いを嗅いでみる。確かに水だと確認したそのグラスを、彰人は一息で空にした。